機関紙「港湾労働」
全港湾が発行する機関紙をPDFファイルにて掲載しております。
過去の内容もご覧いただけます。
私たちの活動情報をより詳しくしていただくために是非ご覧ください。
全港湾は、港湾、トラック、倉庫、関連企業などに働く仲間が
集まった海陸一貫輸送をになう産業別労働組合です。
第47回中央委員会開催!!
2026年1月29日~30日、豊橋市シーパレス日港福にて、全港湾第47回中央委員会が開催され、たたかう全港湾の26春闘方針が確立された。
集会には、中央委員47名、中央執行役員19名、傍聴47名の参加があった。

開会あいさつ 畠山 副中央執行委員長
畠山副中央執行委員長より、青森県東方沖地震への支援や、衆議院選挙の状況、各最上政党が話され、そのうえで26春闘をどうたたかっていくのかの提起がなされた。

議長 関東地方 河村法和中央委員(左)、 東海地方 千頭和達也中央委員(右)
議長団就任のあいさつでは、河村委員が、米軍トランプ大統領の暴挙や物価髙、選挙についての言葉があった。

あいさつ 鈴木誠一 中央執行委員長
鈴木誠一委員長からは、北海道、北陸日本海側にかけての大寒波の中での開催となったことや能登半島に続く青森県東方沖地震での被災者への追悼、被災状況に振られ、いまだに続いている日港協不当労働事件裁判について語られた。そのうえでどういった26春闘をたたかうのか、組合員の声や負託にどう応える春闘にするのか議論をお願いしたいとの挨拶を行った。

あいさつ 竹内 一 全国港湾委員長
来賓である全国港湾竹内中央委員長からは、「全国港湾26年春闘方針のたたかう5本の柱」が提起され、日港協との正常な労使関係の構築や26春闘での大幅賃上げを産別運動として求めていくとの挨拶がなされた。


東北地震についての報告・見舞い贈呈
東北地方本部より「青森県東方沖地震での被災状況といち早い行政への取り組みのお礼と、今後の皆さんのご協力をお願いする」報告がなされた。これを受け、中央本部は「お見舞金」として金一封を贈呈し、今後も寄り添って対応にあたることが確認された。

闘争報告 上條清隆 分会長
「日興サービス分会闘争」の報告がなされ、一向に解決に進んでいない現状と解決促進のための行動を求める発言があった。
主立った質疑は①石炭火力問題、②トラック・バス・タクシー関係、③選挙闘争関係、④人手不足問題、⑤兵站基地関係、⑥特定利用港湾関係、⑦年末年始関係、⑧防災無線、⑨指定事業体関係、⑩最賃関係⑪労基法関係、⑫放射線検査関係の件など、多岐にわたる多くの質問意見が提起されました。
特に衆議院選挙に関する質疑が大変多く、短期間でどう取り組むのかや若い人に選挙運動の経験がないため取り組みにくい、また、過去の政治に対しての勉強や政党の再編の動きなど具体的な学習が常日頃から必要ではないかなど、大変厳しい質疑も出された。







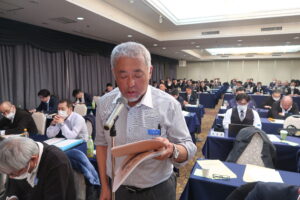












その後各地方本部より春闘要求額、日程、各地方独自の付帯要求の発表があり中央執行委員会で取りまとめ、総括答弁にてまとめを行った。

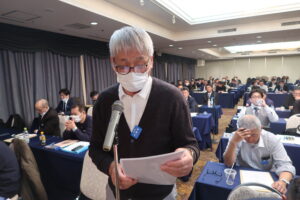



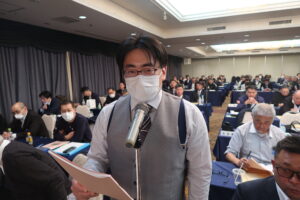




現在衆議院議員選挙がたたかわれております。新党結成というようなことがありまして、大変複雑な、また時代の変化を感じるところの選挙ということになっています。今から30年ほど前、89年の労戦統一の頃なんていうのは、わが組織も大会や中央委員会などで本当にイデオロギー対立がありました。もう腹を割った、本当に激しい議論がされていたと記憶をしています。89年に労戦統一されて以降は、労働組合、日本の労働組合が弱体化をしていくのを私はそのまま見て来ました。やはり昨日のご発言じゃないですけれども、そういった意味で今回の選挙、選挙が終わってから、たたかい抜いてから、この選挙といいますか、選挙結果とその後のゆくえを見定めながら、私たち全港湾はどうするべきか、ということを問うて行きたいというふうに思います。
その上で今回いろいろな課題、さまざまな意見が出されました。松永書記長の答弁がそのままであります。そういったことで、ここにいる全員、それから全国の全港湾の組合員が課題を共有できたというふうに思っております。この26春闘をたたかう上での課題が共有できて、そして各地本においては中央本部提案であります統一要求、基本給一律4万円、いわゆる目標水準としては6%の獲得ということを掲げて、この春闘、今は1月末でありますけれども、解決は4月の末、ゴールデンウイークの前後になる長丁場のたたかいとはなると思いますけれども、ここにいる皆さんが各々の持ち場、各々の港に帰られて精一杯たたかわれて、そして全港湾の団結を日本の、世界の、この世の中に見せつけるという春闘をたたかっていただくことをお願いしたいと思います。

閉会あいさつ 橋崎 副委員長
閉会の挨拶橋崎副委員長からは、選挙闘争・春闘闘争については真剣に議論し、組合員に伝えてほしい。結論も大事だが過程も大事、しっかり総括してほしい。との挨拶があった。

